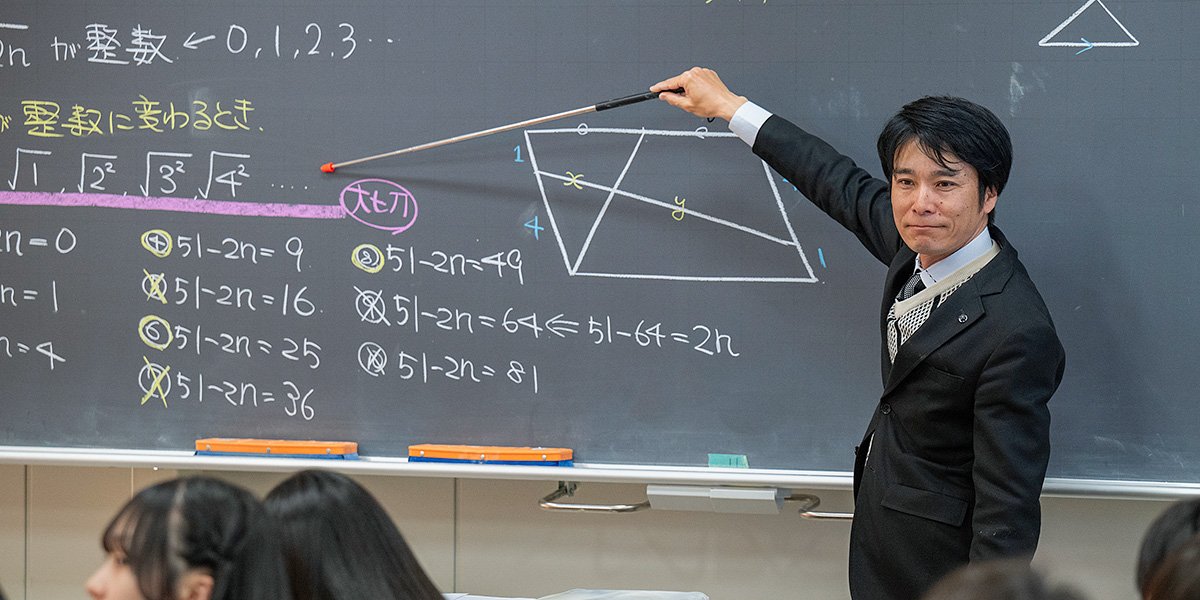いじめ防止対策について
土浦日本大学中等教育学校いじめ対策基本方針
はじめに
本校では,いじめの問題に厳正に対処するために,「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という)第13条の規定に基づき,また「いじめの防止等のための基本的な方針」と「茨城県いじめ防止基本方針」(以下,「県の基本方針」という)を斟酌し,いじめの防止等に取り組むために,『土浦日本大学中等教育学校いじめ対策基本方針』(以下,「土浦日本大学中等教育学校基本方針」という)を策定いたしました。
この「土浦日本大学中等教育学校基本方針」に基づき,学校校務分掌に「いじめ対策室」を設置し,学校,地域住民,家庭,その他関係者と協力して,いじめの防止等に真摯に取組んでおりますので,本校に関係する皆様方のご理解とご協力をお願いします。
令和7年4月
土浦日本大学中等教育学校 校長 堀切 浩一
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(1) 基本理念
いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。本校では「いじめ」の芽となる仲のいいグループ内での行動に注意を向けるとともに,「いじめ」を黙認しない生徒集団を作り上げることによって,全ての生徒がいじめを行なわず,「いじめを認識しながらこれを放置することがないこと。」また,「いじめは,いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。」ということについて,生徒が十分に理解できるようにすることを旨とし,いじめの防止等のための対策を講じる。
(2) いじめの禁止
法第4条「いじめは行ってはならない。」の遵守の徹底を図る。
(3) 学校および教職員の責務・教職員の認識すべき事項
いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,いじめが行なわれず全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,保護者や関係機関との連携を図りながら,学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組む。また,いじめが疑われる場合は,適切かつ敏速にその問題に対応し解消を図るとともに, その再発の防止に努める。
いじめ防止等に関しては,以下の4点を全教職員が認識して取組む
ア)いじめはどの生徒にも起こりうる,またいじめはどの生徒も被害者にも加害者にもなりうるため,日常的に生徒の行動を把握する。
イ)いじめの未然防止には,生徒が主体的に参加できるような授業づくりや集団づくり,学校づくりを行う。
ウ)いじめは大人が気付きにくい形で行われるため,早期発見には,ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いをもって,積極的に認知する。
エ)いじめの報告を受けた場合,特定の教職員で抱え込まず,組織的に被害生徒を守り,加害生徒に毅然とした態度で指導をする。
(4) 目標
いじめの防止等の取組については,以下の5つの取組の徹底を図ることを本校の取組み目標とする。
ア) 未然防止への取組の徹底
イ) 早期発見への取組の徹底
ウ) 早期解消への取組の徹底
エ) 関係機関との連携の徹底
オ) 教職員研修の充実の徹底
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1) 基本施策
① いじめの未然防止
ア)学校の最重点目標の一つに「頑張っている者が正当に評価される学校」を掲げ,一生懸命頑張っている者や弱い者いじめをしない,見過ごさないことに組織的に取り組む。
イ)生徒の道徳心を培い,自己有用感や共感的理解の能力を高め,心の通う人間関係を築くため,さまざまな教育活動を通して道徳教育および体験活動等の充実を図り,その具体的な指導内容を年間計画に体系的に盛り込む。
ウ)心の通じ合う生徒同士の「絆」づくりをすすめ,ホームルームを何でも話し合える「居場所」にするとともに,いじめに向かわない人間関係・環境づくりに努める。
エ)集団の一員としての自覚や自信を育むことにより,互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。
オ)教職員の言動が,生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう,指導のあり方に細心の注意を払う。
カ)保護者ならびに関係機関との連携を図りつつ,いじめ防止のために生徒が自主的に行う生徒会活動に支援を行う。
② いじめ早期発見のための措置
ア)いじめ調査等
いじめは大人の目に付きにくいところで起こり,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことから,いじめを早期に発見するため,在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
ⅰ 生徒対象いじめアンケート調査:年3回(6月・10月・2月)
ⅱ 保護者対象いじめアンケート調査:年2回(6月・10月)
ⅲ 教育相談を通じた学級担任等による生徒からの聞き取り調査:年2回(6月・10月)
イ)いじめ相談体制
生徒および保護者が,いじめに係る相談を行うことができるように次のとおり相談体制の整備を行う。
ⅰ スクールカウンセラーの活用
ⅱ 学校のいじめ相談窓口の設置(いじめ対策室)
ⅲ その他の相談窓口の周知(担任,学年,教科担当,部活顧問,保健室等)
ウ) いじめの未然防止等のための教職員の資質の向上
ささいな兆候であっても,いじめではないかと疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知できるようにするため,いじめ未然防止等のための対策に関する校内研修を年間計画に位置づけて実施し,いじめ未然防止等に関する教職員の資質向上を図る。
③ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒および保護者が,インターネットを通じて行われるいじめを未然防止し,また効果的に対処できるように,必要な啓発活動として,情報モラル研修会等を行う。
(2) いじめ防止等に関する措置
① 「土浦日本大学中等教育学校いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という」の設置
ア) 会議は次の者で構成する。
校長,副校長,教頭,いじめ対策室長,教務主任,生徒指導主任,学年主任,養
護教諭,学校カウンセラー,その他校長が必要と認める者。
イ) 上記の構成員のほか,校長が必要と認める場合は,専門的な知見を有する者などを
臨時に構成員にすることができる。
ウ) 校長は会議を総理し,会議を代表する。
エ) 会議は次に上げる事務を所掌する。
ⅰ 本校のいじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作
成・実行・検証・修正を行う。
ⅱ いじめの未然防止や早期発見に関すること。(アンケート調査・教育相談等)
ⅲ いじめ事案の確認とその対応に関すること。
ⅳ いじめ問題の具体的対応策を検討すること。
ⅴ いじめの相談窓口として相談を受けること。
オ) 会議は校長が召集する。
カ) 会議は月1回の定例会とし,いじめの兆候を把握した時やいじめの相談情報があっ
た時はその都度臨時会とする。
キ) その他,会議の運営に必要な事項は,校長が決定する。
② いじめに対する措置
ア)いじめに係る相談を受けた場合は,速やかに事実関係の把握を行う。
イ)いじめの事実が確認された場合は,いじめを止めさせ,その再発を防止するため,い
じめを受けた生徒・保護者に対する支援と,いじめを行った生徒への指導とその保護
者への助言を継続的に行う。
ウ)いじめを受けた生徒が安心して教育を受けるために必要があると認めときは,保護
者と連携を図りながら,一定期間,別室等において学習を行なわせる措置を講ず
る。
エ)いじめ事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会および所轄警察署
等と連携して対処する。
(3) 重大事態への対処
生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は,次の対処を行う。
① 発生報告
重大事態が発生した旨を,県教育庁学校教育部高校教育課(後期課程)・義務教育課(前期課程)に報告する。
② 実態把握
該当事案に対する調査を実施し,事実関係を速やかに把握する。
③ 被害者保護
いじめの被害を受けた生徒の生命又は身体の安全を確保するとともに,情報を提供した生徒を守るための措置を講ずる。
④ 加害者対応
いじめの加害生徒に対しては,毅然とした対応でいじめを止めさせるとともに,しっかりと寄り添い,いじめを繰り返さないよう指導・支援する。
⑤ 調査結果報告
調査結果については,県教育庁学校教育部高校教育課または義務教育課に報告するとともに,いじめを受けた生徒と保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を積極的にかつ適時,適切な方法で提供する。
⑥ 知事への報告
上記調査結果については,県教育庁学校教育部高校教育課または義務教育課を通じて,県知事に報告する。
⑦ 解消と再発防止
いじめの被害を受けた生徒に対しては,継続的な心のケア等,落ち着いて学校生活をおくることができるための支援や,適切な学習に関しての支援等を行う。
⑧ 同種事態の発生防止
当該事態の事実に真摯に向き合い対応することによって,同種の事態の発生を防止する。
(4) 学校評価における留意点
いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,以下の①~⑤の5項目に関しての評価基準を本校の学校評価項目に加え,適正に本校のいじめ問題対応の取組みを評価する。
① 未然防止の評価基準
いじめの未然防止に関する取り組みに関すること。
ⅰ 生徒の自己指導能力を高めることができた。
ⅱ 生徒の自己有用感を高めることができた。
ⅲ 生徒の規範意識を高めることができた。
ⅳ 生徒が教職員と相談しやすい関係を構築できた。
ⅴ 情報モラル教育を推進できた。
② 早期発見の評価基準
いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。
ⅰ いじめの早期発見に努めることができた。
ⅱ 保護者から学校へ相談できる関係が構築できた。
ⅲ 複数の相談窓口を生徒や保護者へ周知できた。
③ 早期解消の評価基準
いじめへ対処するための取り組みに関すること。
ⅰ 被害者の心のケアができた。
ⅱ 適切にいじめの事実を確認できた。
ⅲ 加害者に対しては,いじめをやめさせることができた。
ⅳ 重大事態の調査をし,県教育庁学校教育部高校教育課または義務教育課を通じて県知事への報告ができた。(重大事態があった場合)
ⅴ インターネットを通じて行われるいじめの対応ができた。
④ 関係機関との連携の評価基準
いじめ防止の取り組みについて,関係機関との連携に関すること。
ⅰ 保護者と密接に連絡を取り合うことができた。
ⅱ 地域の協力を得ていじめの対応等ができた。
ⅲ 警察,児童相談所,法務局等の関係機関に相談できた。
ⅳ 学校以外の場で起きたいじめに適切に対応できた。
⑤ 教職員研修の評価基準
いじめ防止の取り組みについての教職員の諸研修に関すること。
ⅰ 実践的研修を行うことができた。
ⅱ 事例研究を通して,いじめの対応方法の共通理解を図ることができた。
ⅲ インターネット環境等に関する研修を行うことができた。
以上の評価を通して,いじめへの取り組みが計画通りに進んでいるかどうかのチェックや学校の基本方針等について体系的に見直しを行い,より迅速かつ適切ないじめの防止等の対応にについて検討する。また,必要に応じて年間計画等の修正等を行い,組織的な取組みや,地域及び家庭と連携した,いじめ問題対策の総合的な改善を図る。